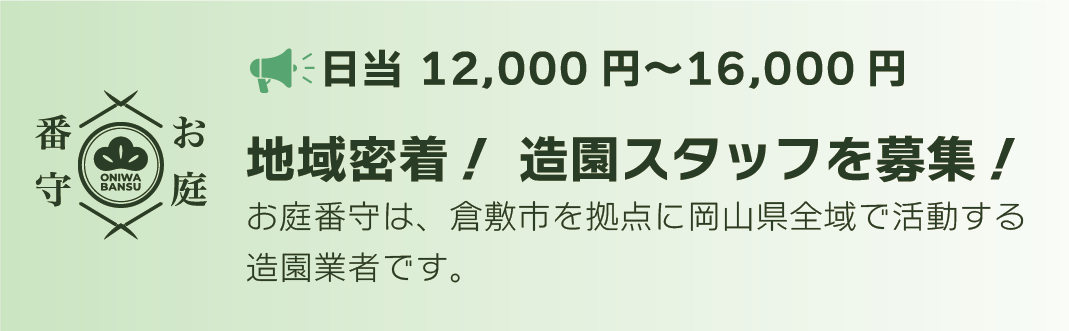こんにちは。町の植木屋で庭師をしている者です。秋が深まって、庭先の柿の木が橙色に色づき始めると、「ああ、今年もこの季節が来たんだな」って、なんだか心が温かくなりますよね。僕が子供の頃、祖父の家の庭にあった大きな柿の木。もぎたてを丸かじりした時の、あの口いっぱいに広がる甘さは、今でも忘れられません。
でも、庭に柿の木があるお宅から、こんな相談をよく受けるんです。「去年はあんなに沢山なったのに、今年は全然ダメで…」「木ばっかり大きくなって、全然実がならないんだけど、どうして?」。
その悩み、もしかしたら「剪定」で解決できるかもしれません。柿の木には、おいしい実をたくさんつけてもらうための、ちょっとしたご機嫌の取り方があるんです。
この記事では、僕が親方や、それこそ祖父から教わった、柿との上手な付き合い方…剪定の秘訣を、余すところなくお話ししようと思います。
そもそも、なぜ柿の木に剪定が必要なの?

「枝を切るなんて、もったいない」「自然のままが一番じゃないの?」その気持ち、すごくよく分かります。でも、おいしい柿を毎年コンスタントに楽しみたいなら、剪定は避けて通れない、むしろ柿への愛情表現なんです。放っておくと、柿の木はちょっとワガママを言いはじめるんですよ。
おいしい実を「毎年」収穫するため
「隔年結果(かくねんけっか)」って言葉、聞いたことありますか?豊作の年と、まったく実がならない不作の年を繰り返す現象のことです。これは、前の年に実をつけすぎて疲れ果てた木が、翌年は休んでしまうために起こります。
剪定で枝の数を調整し、実のなる量をコントロールしてあげることで、木の負担を減らし、「毎年、安定して」おいしい実をつけてもらうことができるんです。いわば、無理させないための健康管理ですね。
木を病害虫から守り、健康に保つため
剪定をしないと、枝はどんどん伸びて混み合っていきます。そうなると、内側の葉っぱまで太陽の光が届かなくなり、風通しも悪くなる。ジメジメして薄暗い場所…もう、病原菌や害虫たちにとっては最高のパーティー会場ですよ。
ヘタムシ(カキミガ)なんかの害虫被害も、枝が混み合っていると広がりやすい。剪定で風と光の通り道を作ってあげることは、柿の木を病気から守るための、何よりのワクチンなんです。
収穫や手入れをしやすくするため
柿の木って、放っておくとびっくりするくらい大きくなりますよね。僕がお手入れに伺うお宅でも、脚立を使ってもてっぺんの実に手が届かない、なんてことは日常茶飯事。
剪定で高さを抑えて、枝を手の届く範囲に配置してあげることで、収穫はもちろん、消毒などの普段のお手入れが、びっくりするくらい楽になります。安全に作業するためにも、これはすごく大事なこと。
柿の剪定、いつやるのが正解?【時期を間違えると実がならない】

やる気が出てきたところで、まず押さえておきたいのが剪定のタイミング。柿の木は、切る時期を間違えると、とたんに機嫌を損ねて実をつけてくれなくなります。ここは絶対に外せないポイントです。
本番は冬!落葉後の「休眠期剪定」(12月~2月)
柿の木の剪定に最も適した時期。それは、葉がすべて落ちて、木が眠りについている12月から2月の寒い時期です。なぜこの時期かというと、理由がちゃんとあります。
- 枝が見やすい:葉っぱがないから、木の骨格や枝の混み具合が一目瞭然。「どの枝を切るべきか」がすごく判断しやすいんです。
- 木へのダメージが少ない:休眠期なので、人間で言えば麻酔がかかっているような状態。この時期に切れば、木の体への負担が最小限で済みます。
来年の秋に、たわわに実った柿を収穫するための、いわば仕込みの作業。この冬の剪定が、一年間の柿の出来を決めると言っても過言ではありません。
夏(7月~8月)の剪定は、あくまで「補助」
「夏にも剪定するって聞いたけど?」はい、夏にも剪定をすることはあります。でも、これはあくまで補助的なもの。目的は、茂りすぎた葉を軽く間引いて、日当たりや風通しを改善すること。ひょろひょろと勢いよく伸びすぎた枝(徒長枝)を軽く切る程度に留めます。
夏の時期にバシバシと強く剪定してしまうと、木が弱ってしまうだけでなく、後述する大事な「花芽」を切り落としてしまう危険性が大!なので、夏の剪定は「ちょっと込み合ってるから、髪をすいてあげるね」くらいの、ごく軽い気持ちで行うのが鉄則です。
【最重要】これを読まなきゃ始まらない!柿の花芽の秘密

さて、ここからがこの記事の核心部分です。これを理解しているかどうかで、あなたの柿の木の運命が決まります。大げさじゃなくて、本当に。
柿の剪定で、絶対に覚えておかなければいけないルール。それは…
『柿は、前年に伸びた枝の先端付近に、実になる花芽をつける』ということです。
どういうことか分かりますか?
去年の春から夏にかけて、にょきにょきと伸びた新しい枝がありますよね。その枝の、先端から2~4個目くらいまでの芽が、翌年に花を咲かせ、実になるんです。つまりですよ?「伸びすぎたから」といって、去年の枝の先端を全部パチンパチンと切りそろえてしまったら…。
そう、その年は絶望的に実がなりません。悲劇です。この「もったいない切り方」をしてしまっているお庭、本当に多いんですよ…。僕が見て、何度「あぁっ!」と心の中で叫んだことか。
なので、柿の剪定は「どの枝に実がなるか」を見極め、その「実がなる枝(結果母枝)」を大事に残しつつ、不要な枝を取り除く、という考え方が基本になります。先端の芽がふっくらしている、元気の良い枝。それが宝物の枝です。
【実践編】庭師が教える柿の木の剪定手順

お待たせしました。いよいよ実践です。最初は難しく感じるかもしれませんが、手順通りに進めれば大丈夫。さあ、ハサミを手に取ってみましょう!
1.まずは道具の準備から
剪定に必要なのは、剪定バサミと、少し太い枝を切るための剪定ノコギリ。そして安全のための脚立と手袋。太い枝を切った後の切り口に塗る「癒合剤」もあると、病原菌の侵入を防げるので万全です。
2.剪定の基本ステップ
- 木を眺めて、理想の姿をイメージする
いきなり切り始めるのは禁物。まずは木から少し離れて、全体を眺めます。「3年後、この木はどんな形になっているだろう?」「どの枝が邪魔かな?」と、完成形を妄想する時間。これが一番大事。 - 不要な枝を根元から取り除く(間引き剪定)
まずは、明らかに不要な枝を根元から切り落とします。これだけでも、かなりスッキリするはず。下の表にあるような枝を見つけたら、ためらわずに切ってしまいましょう。 - 残す枝の先端を切り詰める(切り戻し剪定)
次に、残すと決めた「実がなる枝(結果母枝)」の剪定です。枝の先端から、ふっくらした良い花芽を3~4個数えて、その少し先で切ります。こうすることで、残した芽に栄養が集中し、質の良い大きな実がなるんです。枝の先端まで芽を残しすぎると、実がつきすぎて小さくなったり、枝が折れたりする原因になります。 - 全体のバランスを整える
最後に、もう一度木から離れて全体を確認。枝が均等に配置され、木の中心まで光が当たるような形になっていれば、剪定は完了です!お疲れ様でした!
こいつは切るべし!不要枝リスト
「不要な枝って言われても、どれのこと?」という方のために、代表的なものをまとめてみました。
| 不要枝の種類 | 特徴 | なぜ切るの? |
|---|---|---|
| 徒長枝(とちょうし) | 上に向かって勢いよく、まっすぐ伸びている太い枝 | 栄養を独り占めする暴れん坊。実もつきにくい。 |
| 内向枝(ないこうし) | 幹の中心に向かって、内側に伸びている枝 | 日当たりや風通しを悪くする元凶。 |
| 交差枝(こうさし) | 他の枝と交差したり、絡みついたりしている枝 | 枝同士が擦れて傷になり、病気の原因になる。 |
| 枯れ枝・病気の枝 | 明らかに枯れている、色が違う、病気の痕跡がある枝 | 見た目が悪いだけでなく、病気の発生源になる。 |
| 下向きの枝 | 下に向かってだらんと垂れ下がっている枝 | 日当たりが悪く、良い実がなりにくい。 |
まとめ
どうでしょう、柿の木の剪定、少しは身近に感じてもらえたでしょうか。柿の剪定は、ただ枝を切る作業ではありません。柿の木の性質を理解して、「君が元気においしい実をつけるには、どうしたらいいかな?」と問いかけ、手助けしてあげるコミュニケーションです。
一番大事なのは、「前年に伸びた枝の先端に実がなる」という柿の木の秘密を、絶対に忘れないこと。これさえ分かっていれば、大きな失敗はしません。
最初は、どの枝を切ればいいか迷うと思います。でも、大丈夫。何年か続けているうちに、不思議と「この枝は来年良い実をつけそうだ」なんて、枝の顔つきが分かってくるものですよ。切った枝の分だけ、来年の秋、甘くて美味しい実があなたを待っています。
そう信じて、まずは一本、ハサミを入れてみませんか?その一歩が、きっと豊かな実りにつながるはずですから。