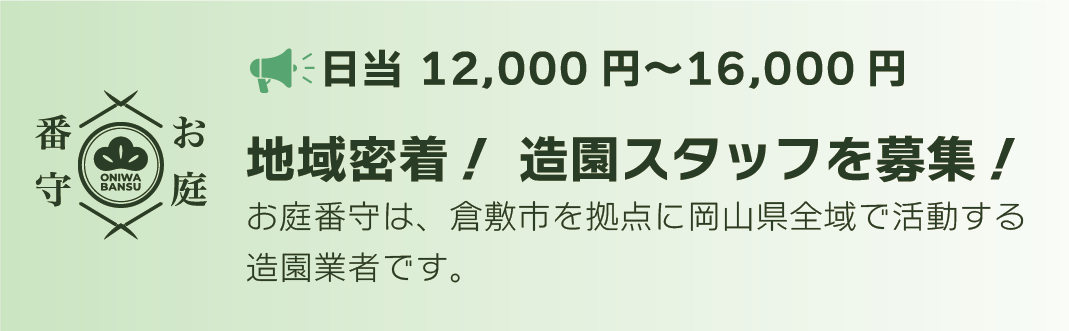こんにちは!庭の片隅で土とハサミにまみれている庭師です。庭木の中でも、やっぱりバラは特別な存在ですよね。その香り、花びらの重なり、色の深み…。一つひとつに物語があるようで、思わず見とれてしまう。
僕も大好きです。でも、その美しさを保つためには、ちょっとした愛情…いや、かなり大事な「剪定」という作業が欠かせません。
「バラの剪定って、なんだか難しそう」「どこをどう切ったらいいのか、さっぱり…」「下手に切って枯らしてしまったらどうしよう」。うんうん、その気持ち、痛いほどわかります。僕だって最初はそうでしたから。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、僕がバラと対話しながら学んできた「季節ごとの剪定」を、カレンダー形式でまるっとお伝えしようと思います。これはもう、バラを美しく咲かせるための、愛の約束事みたいなもんですよ。
なぜバラに剪定は欠かせないの?~美しく咲いてもらうための約束事~

「植物なんだから、自然に任せておけばいいんじゃないの?」そう思う方もいるかもしれません。でも、バラはちょっと特別。というか、かなりのかまってちゃん。
放っておくと、すぐにヘソを曲げてしまうんです。剪定は、そんなバラの機嫌をとりつつ、最高のパフォーマンスを引き出してあげるための、超重要なコミュニケーションなんです。
約束事1:良い花を咲かせるため
バラは、その年に新しく伸びた枝に花を咲かせる性質があります。剪定をしないで古い枝ばかり残しておくと、木全体のエネルギーが分散してしまって、新しい枝が伸びにくくなる。
結果、花が小さくなったり、数が減ったりするんです。切ることで新しい枝の発生を促し、「ここにエネルギーを集中させて、立派な花を咲かせるんだぞ!」とバラに教えてあげる。それが剪定の最大の目的ですね。
約束事2:病気や害虫から守るため
枝が混み合ってジャングルのようになると、風通しが悪くなって湿気がこもります。これ、黒星病やうどんこ病といった、バラの大敵である病原菌にとっては天国みたいな環境。
まさにウェルカム状態。剪定で枝を整理して、株元まで風と光が届くようにしてあげることで、病気の予防に繋がります。健康第一、これは人間もバラも同じですよね。
約束事3:美しい姿を保つため
放っておくと、枝は四方八方に伸び放題。なんだかまとまりのない、ぼさぼさ頭みたいな姿になってしまいます。剪定は、バラの骨格を作り、将来どんな姿に育ってほしいかをデザインする作業でもあります。
特に冬の剪定は、春からの美しい姿を決定づける、いわば設計図を描くようなもの。これがビシッと決まると、本当に見違えますよ。
これだけは揃えたい!バラ剪定の三種の神器

さあ、バラと対話する準備をしましょう。立派な道具をたくさん揃える必要はありません。でも、これだけは「ちょっと良いもの」を用意してほしい、という僕の相棒たちを紹介します。
- 剪定バサミ:言わずと知れた主役。バラの枝は意外と硬いので、しっかりした作りのものを選んでください。切れ味の悪いハサミで切ると、枝の細胞を潰してしまって、病気が入る原因にもなる。スパスパ切れるハサミは、作業も楽しいし、バラへのダメージも最小限。まさに一石二鳥です。
- 革手袋:バラのトゲ、あれは本当に厄介。僕も数えきれないほど傷だらけになりました。「これくらい平気」なんて素手で挑むと、後で泣きを見ることになりますよ。手首までしっかり覆ってくれる、厚手の革手袋は必須アイテム。怪我なく楽しく作業するための、自分へのお守りです。
- 剪定ノコギリ:剪定バサミでは歯が立たない、古くなった太い枝を切るときに使います。出番は少ないかもしれませんが、いざという時にないと本当に困る。折りたたみ式のコンパクトなもので十分です。
あ、それと!作業の前後に、剪定バサミをアルコールや熱湯で消毒するのを忘れずに。他の植物から病気をうつさないための、大切なマナーです。
【バラ剪定カレンダー】季節ごとの作業と目的

ここからは、いよいよ本題。一年を通したバラの剪定を、カレンダー形式で見ていきましょう。バラの気持ちになって、それぞれの季節で何をしてほしいのかを感じながら作業するのがコツですよ。
| 季節 | 時期 | 剪定の種類 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 冬 | 12月~2月 | 本剪定・強剪定 | 樹形の骨格作り、春の開花準備(最重要!) |
| 春 | 5月~6月 | 花がら切り | 二番花を咲かせる、体力の消耗を防ぐ |
| 夏 | 7月下旬~9月上旬 | 夏剪定・軽剪定 | 株を休ませる、秋花の準備、風通しを良くする |
| 秋 | 10月~11月 | 花がら切り・整枝 | 咲き終わった花を摘む、冬に向けての準備 |
【冬:12月~2月】一番大事なメインイベント!
バラが葉を落として休眠しているこの時期。これが一年で最も重要な「本剪定」のタイミングです。見た目は寒々しいけど、バラは春に向けてエネルギーをじっくり溜め込んでいる。ここでバッサリ切ることで、春に「待ってました!」とばかりに力強いシュート(新しい枝)を吹かせるんです。
え、こんなに切るの!?って、最初は絶対思います。僕もそうでした。でも、ここでためらっちゃダメ。四季咲きの木立ち性バラなら、全体の高さの半分から、思い切って3分の1くらいまで切り戻します。
ポイントは、細くて弱々しい枝、枯れ枝、内側に向かって伸びる枝を根元から整理して、太くて元気な枝を3〜5本残すこと。そして残した枝を、外側に向いている芽(外芽)の5mm〜1cm上で、斜めに切る。
こうすることで、新しく伸びる枝が外に広がって、カップのような美しい樹形になるんです。まさにバラの骨格矯正。ここで春の花が決まる!と言っても過言じゃない。はっきり言って、一番気合が入る作業です。
【春・夏・秋】花を長く楽しむためのメンテナンス
冬の剪定さえ乗り越えれば、あとは比較的気楽なメンテナンス作業が中心です。
春(5月~6月)の花がら切り:
一番花が咲き終わったら、次の花(二番花)を咲かせるために「花がら切り」をします。咲き終わった花をそのままにしておくと、バラは実(ローズヒップ)を作ろうとして、そっちに体力を使っちゃう。
だから「君の仕事はまだ実を作ることじゃないよ、次も綺麗な花を咲かせておくれ」と、花首からではなく、5枚葉がついている枝の上で切ってあげます。これが次の花芽を出すスイッチになるんです。
夏(7月下旬~9月上旬)の夏剪定:
人間も夏バテするように、バラも日本の蒸し暑い夏はちょっと苦手。この時期に咲く花は小さくて、すぐに開いてしまうことが多いです。そこで、秋に立派な花を咲かせるために、一度リフレッシュさせてあげるのが夏剪定。
冬剪定のようにバッサリではなく、全体を軽く3分の2くらいの高さに切りそろえるイメージ。風通しを良くして、夏を乗り切り、秋の開花に備えてもらう。いわば、秋への助走ですね。
秋(10月~11月)の整枝:
秋バラを楽しんだ後も、花がら切りはこまめに行います。冬が近づくにつれて、深い剪定はしません。伸びすぎた枝を軽く整える程度にして、バラが冬眠の準備をするのを静かに見守ってあげましょう。
ちょっと特別扱い?つるバラの剪定と誘引

ここまで主に木立ち性のバラの話をしてきましたが、つるバラは剪定の考え方がちょっと違います。つるバラは枝を長く伸ばして、そこに花を咲かせるのが魅力。だから、冬でもバッサリ短くはしません。
つるバラの冬作業のメインは「剪定」と「誘引」。誘引っていうのは、伸びた枝をフェンスやアーチに結びつけて、形を整えてあげる作業のこと。
まず、枯れ枝や3年以上経った古い枝(花付きが悪くなる)を根元から切ります。そして、その年に伸びた元気な新しい枝を残し、それをできるだけ水平に近い角度で誘引していく。なぜ水平かというと、枝を横に倒すことで、それぞれの節から花を咲かせる短い枝が出やすくなるからなんです。
これをやるとやらないとでは、春の花の数が天と地ほど変わってくる。まさに腕の見せ所。壁面をキャンバスに見立てて、どんな絵を描こうかと考える時間は、庭師にとって至福のひとときだったりします。
まとめ
ふう、バラの剪定について語り始めると、どうにも止まらなくなってしまいますね。季節ごとにやることは違って、最初はちょっと戸惑うかもしれません。でも、結局のところ、剪定って「バラとの対話」なんです。
「今は疲れてるんだね、少し休もうか(夏剪定)」
「春に向けて、一緒に準備しようぜ!(冬剪定)」
「君は本当に綺麗だね、次も頼むよ!(花がら切り)」
そんなふうに声をかけるような気持ちでハサミを握れば、きっとバラも応えてくれます。完璧じゃなくていいんです。ちょっとくらい失敗したって、バラは強いから大丈夫。…たぶんね。
何より大事なのは、バラを想うあなたのその気持ち。この記事が、あなたとあなたのバラとの対話の、ささやかな手助けになれたら、心から嬉しいです。