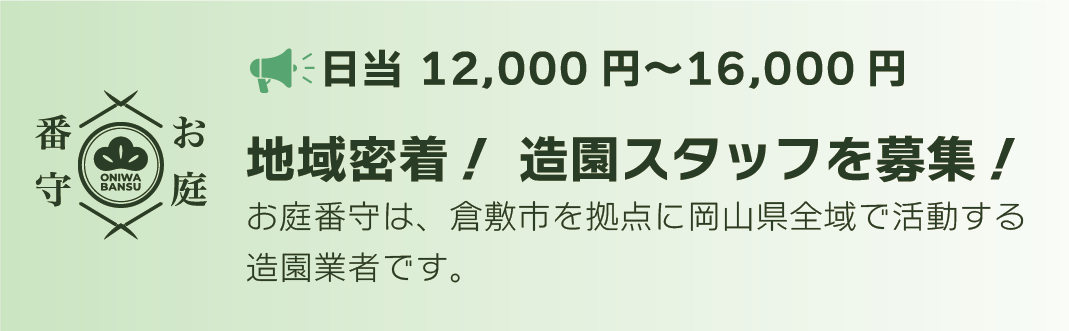庭木の元気がなくなってきた……
そんな悩みを感じたら、もしかすると「肥料不足」が原因かもしれません。
そこでこの記事では、庭師の監修のもと、初心者でも失敗しない庭木の肥料のあげ方を徹底解説いたします。
「どんな肥料を選べばいいの?」
「いつ・どのくらい与えるのが正解?」
そんな疑問にお答えしていきます。
季節別のコツや注意点、おすすめの肥料の種類まで網羅した完全ガイドですので、ぜひ最後まで読んで、庭木を元気に育てるヒントを掴んでくださいね。
肥料をあげる理由と基本知識

庭木に肥料が必要な理由とは?
庭木は自然の山林や原野と違い、限られたスペースと土壌で育てられています。
鉢植えや庭植えでは、土の栄養が雨水や根の吸収で徐々に失われていくため、放置すると栄養不足に陥りやすくなります。
肥料を適切に補うことで、葉の色や艶が良くなる、枝ぶりが整う、花つきや実つきが向上するといった生育面での効果が期待できます。
また、病害虫への抵抗力がつく、根がしっかり張るなど、植物本来の生命力を高める役割もあります。
肥料の三大要素(N・P・K)とは?
植物の健やかな生育に欠かせないのが、肥料に含まれる三大栄養素(N・P・K)です。
それぞれの意味は以下のとおりです。
・N(窒素):葉や茎の成長を促し、葉色を濃く保つ
・P(リン酸):花や果実の形成を助け、開花・結実を促進
・K(カリウム):根の張りを良くし、病害虫や乾燥への耐性を高める
これらをバランス良く配合した「NPKバランス肥料」は、庭木全体の健康維持に最適です。
肥料が与える効果と注意点
適切な肥料を与えることで、以下のようなメリットがあります。
・葉が艶やかで濃い緑色に
・花の開花数や実の収穫量が増加
・根がしっかり張り、全体の成長が安定
・病気や虫への抵抗力がアップ
しかし、与えすぎによる肥料焼け(根焼け)や栄養バランスの崩壊にはご注意ください。
特に窒素過多になると、葉ばかりが茂って花芽がつきにくくなることもあります。
肥料は多ければいいわけではなく、種類・量・タイミングを見極めて使うことが重要です。
有機肥料と化成肥料の違い

肥料には有機肥料と化成肥料の2種類があります。
それぞれの特徴を確認していきましょう。
有機肥料(ゆうきひりょう)
・特徴:動植物由来の自然素材。土を豊かにする効果もあり。
・主な成分例:油かす・骨粉・鶏ふん・魚かす
・メリット:持続性があり、土壌改良にも役立つ
・デメリット:においが出る/効果がゆっくり
化成肥料(かせいひりょう)
・特徴:人工的に成分を配合した肥料。即効性が魅力。
・主なタイプ:粒状肥料、緩効性肥料
・メリット:手軽で効果が早い/分量調整がしやすい
・デメリット:与えすぎると根焼けのリスクも
こちらを表にまとめると、以下の形になります。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 有機肥料 | 動植物由来(油かす・骨粉・堆肥など) | ・土壌を豊かにする ・緩やかに効くので安全性が高い | ・効果が出るまで時間がかかる ・ニオイが気になる場合も |
| 化成肥料 | 科学的に成分を配合した肥料 | ・即効性がある ・成分が安定している | ・使いすぎると根を傷めやすい ・土壌を劣化させる可能性 |
初心者や庭木の根や土壌環境を育てたい場合には、ゆっくり効く有機肥料がおすすめです。
基本的には有機肥料を使用し、急ぎで回復させたい場合のみ化成肥料を補助的に取り入れるのが安心の使い方といえるでしょう。
庭木に与える肥料の種類と特徴
庭木に使う肥料は、使うタイミング・成分・形状によって大きく4種類に分かれます。
初心者でも迷わず選べるように、それぞれの特徴をまとめましたので、ご確認ください。
肥料の与え方による分類
元肥(もとごえ)
・タイミング:植え付け時や、春先の生育前
・特徴:あらかじめ土に混ぜ込むことで、栄養をじっくり供給
・おすすめ肥料:油かす、緩効性化成肥料、堆肥
追肥(ついひ)
・タイミング:成長期(春~秋)の途中
・特徴:植物の様子を見ながら追加で与える肥料
・おすすめ肥料:液体肥料、置肥、有機配合肥料
寒肥(かんごえ)
・タイミング:1月〜2月の休眠期(落葉後)
・特徴:地中にゆっくり効いて、春の芽吹きに備える
・おすすめ肥料:完熟たい肥、油かす+骨粉などの有機肥料
芽出し肥(めだしごえ)
・タイミング:2月下旬~3月ごろ(新芽が動き始める前)
・特徴:春の新芽や花芽の生育を後押しする
・おすすめ肥料:リン酸(P)を多く含む肥料
庭木の種類・年齢による肥料の使い分け

庭木に与える肥料は、木の年齢や種類によって選び方が変わります。
以下では、「若木」「成木」「花木・果樹」などに分けて、適切な肥料のタイプと与えるタイミングを解説しますので1つずつ確認していきましょう。
若木(植えてから3年以内)
若木は根が未発達でデリケート。
過剰な肥料は「根焼け」を起こしやすいため、慎重に与える必要があります。
・肥料のタイプ:液体肥料、水肥(希釈して使えるもの)
・タイミング:春〜秋の生育期に月1回程度
・ポイント:根元から離れた場所に少量与えるのが基本
例)モミジ、サツキ、アジサイなどの観賞用低木
成木(植えてから4年以上)
根が広がり、十分な吸収力を持つようになるため、栄養管理で全体のバランスを整えることが重要になります。
・肥料のタイプ:有機肥料(油かす、骨粉)、緩効性化成肥料
・タイミング:春の「元肥」、秋の「お礼肥」が基本
・ポイント:寒肥(1〜2月)で休眠中に養分を蓄えると◎
例)シマトネリコ、ヤマボウシ、イロハモミジなどの中高木
花木・果樹など実をつける庭木
花や実を美しく豊かにつけるには、リン酸(P)成分が多めの肥料が効果的です。
・肥料のタイプ:果樹・花木専用肥、リン酸高配合の有機肥料
・タイミング:
春)芽出し肥(開花・実りに向けて)
秋)お礼肥(花後・収穫後に体力回復)
※必要に応じて夏の追肥で栄養補給
・ポイント:花木は花芽形成前、果樹は開花直後にリン酸を多く含んだ肥料を与えると効果的
例)バラ:芽出し肥+リン酸重視の追肥が必須、ブルーベリー:酸性土壌に対応した専用肥料を選ぶ、柿・梅・柑橘類:お礼肥と寒肥をセットで与えると翌年の実つきが向上
庭木の状態に応じた使い分け
| 状態 | 肥料の工夫 |
| 葉の色が薄い・黄ばんでいる | 窒素(N)をやや多めに含む肥料を |
| 花が咲かない・実がつかない | リン酸(P)多め+日当たりと剪定もチェック |
| 根張りが弱い・ぐらつく | カリウム(K)を意識し、堆肥・腐葉土の併用もおすすめ |
形状による分類|粒状・液体・置肥の使い分け
| 種類 | 特徴と使い方 | 向いている場面 |
| 粒状肥料 | 土に混ぜる or 根元にまく。ゆっくり効く | 長期間放置しやすい場所や寒肥・元肥に最適 |
| 液体肥料(=水肥) | 水に溶かしてジョウロで与える。効果が早い | 生育期の追肥や若木への少量施肥に◎ |
| 置肥(おきごえ) | 土の上に置くだけ。雨でじわじわ溶ける | 室内鉢植えや管理の手間を減らしたい場合 |
一般的な家庭で使われる肥料
| 肥料名 | 種類 | 特徴 |
| 油かす | 有機・固形 | 元肥・追肥に使える。花木に最適。 |
| 骨粉 | 有機・粉状 | リン酸が豊富。果樹や球根に◎。 |
| ハイポネックス | 化成・液体 | 速効性あり。初心者でも扱いやすい。 |
| マグァンプK | 化成・緩効性 | 元肥向き。成木の地植えにも対応。 |
このように、与えるタイミング × 肥料のタイプ × 庭木の状態によって、最適な肥料は異なります。迷ったときは、「目的」「効果の早さ」「植物のタイプ」の3点を軸に選ぶと失敗しにくくなります
肥料を与えるタイミングと季節の違い

庭木に肥料を与える時期は、季節・地域・庭木の状態によって最適なタイミングが異なります。ここでは、それぞれの違いと注意点を詳しく見ていきましょう。
春(3〜4月)|成長のスタートを後押しする「芽出し肥」
・目的:新芽の発芽や花芽の成長を促す
・向いている肥料:リン酸(P)を多く含む有機肥料や速効性の液体肥料
・おすすめの庭木例:モミジ、金木犀、サクラ、ツツジ など
春は植物が眠りから目覚めるタイミング。
この時期に栄養が不足すると芽吹きが弱くなるため、芽出し肥はとても重要です。
夏(6〜7月)|暑さ対策と体力維持のための「追肥」
・目的:暑さに負けない体力を維持する
・向いている肥料:速効性の液体肥料や水肥、即効タイプの化成肥料
・注意点:気温が高すぎる真夏日(30℃以上)を避け、涼しい朝か夕方に行う
特に果樹や花木はこの時期に追肥をすることで、夏の生育を安定させ、秋の収穫・開花に備えることができます。
秋(9〜10月)|「お礼肥」として、来年の花つき・実つき強化
・目的:夏の成長を支えた庭木に栄養を与え、来年の準備をする
・向いている肥料:有機配合肥料やリン酸中心の肥料(花木・果樹に最適)
・おすすめの庭木例:柿、梅、ツバキ、アジサイなど
「お礼肥(おれいごえ)」と呼ばれ、今年の成果に感謝し、来年に向けて備える大切なタイミングです。
冬(12〜1月)|じっくり効かせる「寒肥」で春に備える
・目的:休眠期のうちに根のまわりに栄養を蓄える
・向いている肥料:堆肥、油かす、骨粉などの有機肥料
・注意点:凍結や雪が多い地域では地面が凍る前に施す
特に寒冷地(北海道・東北など)では11月中に寒肥を済ませておくと安心です。
地域差にも注意|関東・関西・寒冷地の違い
・関東・関西の平野部:一般的な施肥カレンダーでOK
・北海道・東北・山間部:地温が下がる前(春・秋は早めに)
・沖縄など温暖地域:生育期間が長いため、施肥回数が多くなる傾向あり
庭木の成長段階で見る肥料のタイミング
| 段階 | 肥料の考え方 | ポイント |
| 植え付け直後 | 肥料は控えめに | 根が活着するまでは過剰NG |
| 幼木(1~3年) | 成長優先、液体肥料中心 | 定期的な追肥で育成サポート |
| 成木(4年以上) | 季節ごとの施肥が重要 | 春・秋・冬の年3回が目安 |
庭木の種類別おすすめ肥料例【初心者向け】
常緑樹(ツバキ・カシなど)
1月に寒肥、5月に追肥、9月に秋肥が基本
落葉樹(モミジ・梅など)
芽吹き前の2〜3月に芽出し肥、7月に追肥
果樹(柿・レモン・ブルーベリーなど)
開花前後にリン酸を多く含む肥料が有効。実の収穫後にもお礼肥を忘れずに
肥料のあげ方の基本とポイント
肥料のあげ方の基本とポイントにつきまして、ネットで検索したときに一般的に出てくる内容は以下の通りです。
地植えと鉢植えで変わる施肥方法
・地植え:根の先端部分にぐるりとまく
・鉢植え:鉢の縁に沿って肥料を置くのが基本
肥料の適切な量と与え方
肥料は少量から始め、樹勢を見ながら徐々に増やすのが安全。
製品ごとの説明をよく確認することが大切です。
肥料やりでよくある失敗と注意点(根焼け・やりすぎ)
・一度に大量に与えると根を傷める原因に
・土壌の乾燥状態で肥料をまくと吸収しづらく逆効果
初心者が覚えておきたい肥料やりのコツ
スコップ不要の簡単な施肥方法
置肥タイプやスティック状の肥料がおすすめ。
穴を掘る手間がない
天気と施肥タイミングの関係
雨の前後に施肥すると、肥料が流れてしまう恐れがある。
晴天が数日続くタイミングがベスト
他の作業(剪定・水やり)との兼ね合い
剪定直後の施肥は避ける(樹木がストレス状態)
水やりとセットで肥料を溶かすイメージで
お庭番守で実際にお客様にアドバイスしている肥料のあげ方のコツ

一般的な方法と基本的には変わりませんが、お庭番守では、お客様へのアドバイスとして以下の内容をお伝えしております。
肥料のあげ方としましては、より具体的に以下の方法をお試しください。
根の先、木の枝の端付近の外周に円を描くように10〜20cmぐらい掘り起こす、もしくは木の枝の外周付近に一定の間隔で20cmの穴を掘り起こして、牛糞、油かす、有機肥料を土と混ぜて戻す。
このようにして肥料をあげることで、植物が元気に育ちます。
よくある質問(FAQ)
Q. 有機肥料と化成肥料、どちらがいいの?
A. 土壌改良をしたいなら有機肥料、即効性を求めるなら化成肥料。併用も可です。
Q. 1年中使える肥料ってある?
A. ゆっくり効く有機質の肥料は比較的通年使えますが、季節ごとの最適な施肥がベターです。
Q. 肥料と堆肥って何が違うの?
A. 肥料は栄養素を供給するもの、堆肥は土壌を改善するもの。役割が異なります。
Q. 植えたばかりの苗木に肥料は必要?
A. 根が活着するまで(1〜2ヶ月)は控えめに。元肥で土壌の栄養を整えるだけでOKです。
Q. 雨の日や直後に肥料をあげても大丈夫?
A. 雨直後は避けましょう。肥料が流れてしまうため、晴天の日を選ぶのが理想です。
まとめ
庭木に元気がない、花つきが悪い——そんなときこそ、肥料の見直しが大切です。
この記事では、初心者でも失敗しにくい肥料の与え方を、時期・種類・方法別に詳しく解説しました。
・肥料の基本三要素(N・P・K)を理解する
・季節ごと・庭木の成長段階ごとのタイミングを押さえる
・与えすぎを避け、自然なリズムで施肥する
・有機肥料と化成肥料、粒状・液体などの特性を使い分ける
これらを意識すれば、庭木本来の美しさや力強さがぐんと引き出せるようになります。
「正しく与えること」=「庭木との対話」です。
あなたの庭の木々が、もっと元気に、もっと美しく育っていきますように願っております。
また、より専門的にという方は、お庭番守をご利用ください。