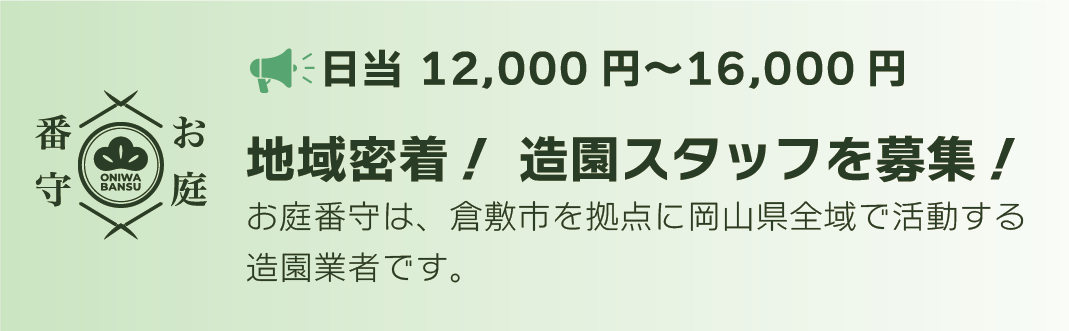松を美しい状態で維持するには、適切な剪定が不可欠です。
松の剪定作業は年に1〜2回ほど行う必要がありますが、剪定の仕方さえ覚えてしまえば、その分維持にかかるコストを抑えられます。
初心者必見!松の木剪定に必要な道具を紹介

松の木の剪定は、剪定バサミとゴム手袋を用いて行います。
また、枝が固くてハサミでは落とせないような場合があるので、剪定用のノコギリも用意しておきましょう。
服装については、松の葉の先端は鋭く、刺さってしまうおそれがあるので、長袖長ズボンを着用するようにしましょう。
【初心者でもできる】松の剪定方法3選

松の剪定は、季節によって行う作業が変わります。
剪定作業は一般的に初夏と初秋に行いますが、それぞれに適した剪定を行うようにしましょう。
ミドリ摘み
ミドリとは、春先に生えた新芽が、初夏にかけて伸びてしまったしまった状態のことを指します。
新芽が伸びてしまうと、樹形のバランスが悪くなってしまうため、初夏の段階でミドリを落とします。
この際、樹形のバランスを悪くするような枝や、他の枝を覆ってしまうように生えている枝があれば、ついでに剪定バサミで根本から切り落としましょう。
ミドリは秋になると固くなってしまうため、ミドリ摘みを行うのは、まだ芽の柔らかい5〜6月に行うとよいでしょう。
もみあげ
もみあげとは、松の古い葉や多すぎる葉を取り除くことです。
もみあげを行うことで、樹形全体のシルエットを整えて、枝どうしの風通しが改善します。
また、松の葉は柔らかくて引き抜きやすいため、もみあげ作業は素手で行うことが可能です。
枝透かし
枝透かしとは、枯れ枝や、見栄えの悪い枝を取り除くことです。
松全体の樹形を整えられるほか、日光の当たりや風通しをよくできるので、木の健康を保ちやすくなります。
切り落としたい枝を探し、剪定バサミを使って、その枝を根元部分から切り落としてください。
松の適切な剪定頻度とは

剪定作業は、初夏と秋の年2回行うのが理想ですが、手間をかけられない場合は、初夏の1回で済ませてしまっても大丈夫です。
初夏の1回のみに行う場合は、5〜6月ごろに、ミドリ摘みと、もみあげ・枝透かしの作業をまとめて行いましょう。
【初心者が成功するためにも】松の樹形を整える5つのコツ

松の剪定は、初心者のうちは理想の形を作るのが難しいかもしれません。
ここでは、うまく松の剪定を行うためのコツを5つ紹介します。
上から下へ、そして奥から手前に剪定する
松の枝は手で簡単に折れてしまうほどにもろく、枝を切り落とした際に、上から切り落とした枝が、下の枝を折ってしまうこともあります。
そのため、下から上の順番で行うと、手入れした箇所をもう一度整える必要が出てくるので、効率が悪いです。
また、枝や葉も同様に、根本部分を剪定するときに、どうしても手前側が傷ついてしまうので、奥から手前の順で剪定した方が効率的です。
枝ごとにまとまりを作る
松を綺麗に見せるためには、枝ごとにまとまりを作るように意識しましょう。
松の枝はあらゆる角度に伸びていきますが、枝一本一本に着目し、枝ごとで形を作ることで、全体を整えられます。
具体的には、枝ごとに扇型のかたまりをつくり、全体で見た時に、その扇を集めた大きな扇を作るようにすると、全体として風情ある形になります。
短葉法を活用する
短葉法とは、ミドリ摘みの手法の一つです。
通常のミドリ摘みでは、短い芽を少しだけ残しておきますが、短葉法では、すべての芽を取り除いてしまいます。
短葉法を使えば、どのミドリを残すかを考える必要がないため、初心者でも楽に作業ができます。
また、新たな芽を出すのにエネルギーを使うため、短葉法を使った際の仕上がりは、通常よりも小ぶりになりやすいです。
葉の量にアクセントをつける
もみあげをする際は、上部の葉はうすく、下部の葉は濃くすることで、樹形全体で見たときのバランスが良く見えます。
松の木は、上部と下部で光を受ける量が変わるので、上下で濃淡をつけると、自然で美しいバランスになりやすいです。
様々な角度から確認する
松の木の枝を落とす際は、将来の樹形を考えながら、全体を多角的に見るようにしましょう。
具体的には、剪定する枝を「遠く・上・下」という3方向から見ることで、残すべき枝や不要な枝を見極められます。
剪定する前にチェックしたい!松の種類

松の種類は複数ありますが、「五葉松」「赤松」「黒松」の3種類が、日本ではよく見られます。
ここでは、それぞれの松の特徴と、お手入れの仕方について解説します。
五葉松
五葉松は、姫子松という別名があり、その名の通り比較的小ぶりな種類です。
そのため、庭木だけでなく、盆栽としても用いられます。
幹は黒松のように黒いですが、葉の生え方に違いがあり、松かさが特徴的な楕円形になっています。
五葉松は蒸れやすいため、お手入れをする際は、風通しを確保し、地面が完全に乾いているときには水を与えましょう。
赤松
赤松は別名「雌松」とも呼ばれ、日本で数の多い種類です。
幹全体が赤茶色であり、葉は柔らかくて細身です。
赤松は、夏になると木の成長が遅くなるため、夏場は必要に応じて肥料や水を与えましょう。
逆に、寒さには強いため、冬場は手入れの必要がありません。
黒松
黒松は「雄松」とも呼ばれ、海岸沿いをはじめとした、あらゆる環境に対応できる松です。
幹が黒く、葉の先端は鋭く尖っているのが特徴であり、また枝が太いため、大きさも上に高くなりやすいです。
黒松は寒暖ともに対応できる強さがありますが、他の松の種類と比べて、害虫による被害を受けやすくもあります。
そのため、害虫が寄ってくる前に、薬剤などを用いた害虫対策を行っておきましょう。
剪定が難しいなら「お庭番 守」に相談しよう

松の剪定作業は、個人でも行うことはできますが、高所での作業を伴うため、落下などの危険があります。
安全に剪定を済まし、松を美しい状態を長く保つためにも、専門の業者に依頼することをおすすめします。
専門業者を選ぶ際には、信頼できる業者であるか判断するためにも、依頼する周辺エリアの実績があるかどうかチェックするとよいでしょう。
「お庭番守」は、倉敷市で活動している地域密着型の造園業者であるため、倉敷市で松の剪定を依頼したい人におすすめの業者です。
豊富な実績があり、剪定の他にも伐採、抜根、害虫駆除、除草といった幅広いサービスを提供しているため、松の剪定やお庭にまつわる悩みを抱えている方は、一度相談してみるとよいでしょう。
- お庭番守
-
-
- 場所
- 岡山県倉敷市四十瀬531−2 ウィンダムヒルズ 102
- 電話番号
- 080-3051-8880
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 年中無休
- 注記
- 諸状況により、掲載情報から変更されている場合があります。事前に施設・店舗までお問合せいただくか、公式サイト等で最新情報をご確認ください。
まとめ
この記事では、初心者でもできる松の剪定方法や樹形を整えるコツ、松の種類について解説しました。
松の剪定は、年に1〜2回ほど行う必要があり、自身で行えば、維持にかかる費用を大きく抑えることができます。
とはいえ、松は一度剪定をしてしまうと、その箇所からはもう2度と枝は生えてこないため、樹形を美しくつくるのが非常に難しいとされています。
将来を見越した樹形づくりを行いたい方は、プロの庭師や植木屋に依頼することをおすすめします。