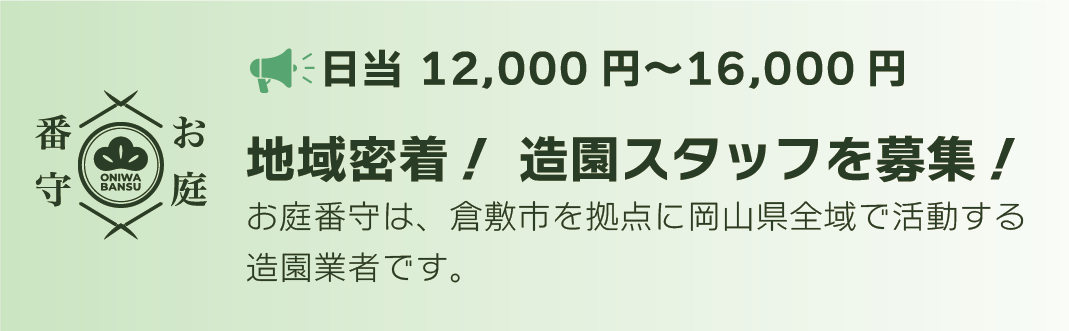金木犀(キンモクセイ)の剪定は、花付きや樹形を美しく保つために欠かせない庭仕事のひとつ。
けれど、「剪定の時期はいつがベスト?」「どの枝を切るべき?」「自己流でも大丈夫?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、庭木の剪定を日々行っているプロの造園業者であるお庭番守が、現場で得た経験をもとに、初心者でもわかる金木犀の剪定方法・時期・注意点を丁寧に解説します。
「費用を抑えつつ、自分で剪定してみたい」
「でも木を傷めたくない」
そんな方に向けて、失敗を防ぐための知識とコツを網羅的にレクチャーいたします。
金木犀の魅力を長く楽しむためのガイドとして、ぜひご活用ください。
金木犀に剪定は必要?

剪定の目的とメリット
金木犀の剪定には、大きく4つ以下のような明確な目的があります。
・花付きの改善
・樹形の維持
・病害虫の予防
・枝の風通しをよくする
それぞれが、美しく健康な木を育てるために不可欠ですので1つずつ確認していきましょう。
花付きの改善
金木犀は、新しい枝に花をつける性質があります。
古くなった枝や混み合った枝を剪定することで、新芽の成長を促し、花の数が増えます。
樹形の維持
剪定することで、自然な丸みのある美しいフォルムを維持できます。
特に金木犀は樹形が乱れやすいため、定期的な形づくりが重要です。
病害虫の予防
枝が混み合うと風通しが悪くなり、カイガラムシなどの害虫がつきやすくなります。
不要な枝を取り除くことで病害虫の予防にもつながります。
枝の風通しを良くする
風通しが悪いと湿気がこもり、根腐れやカビなどの原因になります。
内部の混み合った枝を間引くことで、木全体の健康を保てます。
剪定しないとどうなる?

金木犀を放置して剪定をしないと、以下のようなリスクがあります。
・花が少なくなる(花芽が減少する)
・下枝が枯れる(光が当たらなくなる)
・枝が徒長し、形が悪くなる
・害虫が発生しやすくなる
・落ち葉や枯れ枝が増え、手入れが大変になる
見た目が悪くなるだけでなく、木の寿命を縮める原因にもなり得ます。
数年放置した金木犀を再生するには、大幅な剪定が必要になり、かえって負担が増えることも。
金木犀の剪定に必要な道具
正しい剪定を行うには、適切な道具が欠かせません。
剪定の際は以下の6つの道具をすべて揃えましょう。
剪定バサミ
細い枝のカットに必要。軽量で扱いやすいものを選びましょう。
太枝切りバサミ
太めの枝を切るときに使用。
ノコギリ
主幹や太い古枝に必要。切れ味の良さが重要です。
脚立
高所の枝を剪定する際に必須。安全面にも注意しましょう。
手袋、ゴーグル
トゲや枝でケガをしないよう手や目を保護してから作業してください。
金木犀は硬い枝もあるため、切れ味が良く、手になじむ道具を選ぶのがポイントです。
金木犀の剪定時期はいつがベスト?

基本は「花が終わった直後」
金木犀の剪定に最適なタイミングは、10月中旬~11月上旬の花が咲き終わった直後がおすすめです。
この時期であれば、翌年の花芽がまだ形成されておらず、剪定によって花を減らす心配がありません。
金木犀は新しく伸びた枝先に花芽をつけるため、花後に剪定することで次年度の開花に好影響を与えます。
花が咲く「直前」はNG
一方で、8月下旬〜9月頃の剪定は要注意。
この時期は花芽が形成され始めているため、枝を切るとその年の花が咲かなくなる可能性があります。
冬や春の剪定は?
・冬(12月〜2月):軽い剪定であれば可能。ただし強剪定は避ける。
・春(3月〜4月):伸びすぎた枝の整理など軽めの整枝には向いている。
※注意点
どちらの時期も、花芽ができる場所(枝先)を切らないように慎重に行う必要があります。
真夏(7月〜8月)は避けるべき
金木犀は暑さに弱く、剪定によるダメージが大きくなりやすい時期です。
水分の蒸発量も多く、剪定直後に枯れ込みやすくなるため、強い剪定は避けた方が良いとされています。
地域差にも注意
剪定時期は地域によって多少異なります。
・関東以南の温暖地域:10月中旬〜11月上旬がベスト
・寒冷地(東北など):花の時期がずれるため、11月中旬でも問題ない場合も
各地域の開花タイミングを目安に「花が終わった2週間以内」を目安にすると失敗しづらくなります。
剪定前後にやっておきたいこと
以下の3つのポイントも剪定の際には気をつけましょう。
・水やりや肥料管理も並行して行うと◎
・剪定前に花の終わりを確認する
・剪定後は防腐剤や癒合剤で切り口を保護する
金木犀の剪定方法【基本編】

①剪定前にやるべき準備とは?
1. 花が終わったかを必ず確認
金木犀は、秋に芳香のある小さな花を咲かせます。
剪定のタイミングとして最適なのは、花が終わった直後(10月中旬〜11月上旬)です。
この時期に剪定を行うことで、翌年の花芽に影響を与える心配がなく、健康な枝の選別がしやすくなります。
2. 使用する道具の殺菌・メンテナンス
剪定に使用するバサミやノコギリは、病原菌を媒介するリスクがあります。
事前にアルコールや消毒液で殺菌し、切れ味の確認もしておきましょう。
清潔かつ鋭利な道具は、木に与えるダメージを最小限にします。
3. 樹形の全体バランスをチェック
剪定に入る前に、樹木の全体像を観察することが重要です。
上から下までの高さ、横幅、内側と外側の枝の混み具合を目で確認し、どこを残し、どこを剪定すべきかの計画を立てておきます。
②基本的な剪定手順と切るべき枝
1. 枯れ枝や病害虫がついた枝を除去
枯れている枝や、黒ずみ・カビ・虫食いのある枝は、剪定の最優先対象です。
これらを残すと、木全体に病気が広がったり、成長の妨げになります。
根元から丁寧に切り取るようにしましょう。
2. 内向きの枝・絡み合った枝を間引く
金木犀は放っておくと内側に枝が込み合っていく傾向があります。
風通しが悪くなると、害虫が発生しやすくなります。
内向きに伸びる枝や、交差して擦れ合っている枝を間引くことで、健全な樹形が維持できます。
3. 樹形を整えるために外側の枝を切り戻す
外側の枝は、全体のバランスを保ちつつ、軽く剪定します。
枝先を数cm単位で調整することで、ナチュラルな球形に近づけることができます。
切りすぎには注意が必要です。
金木犀の目的別 剪定テクニック

①低く仕立てたい場合の剪定方法
・太めの枝は、付け根近くでカット(節を意識して切る)
・地面に近い枝も、思い切って除去可能
・剪定後には癒合剤(傷口保護剤)を使うと安心
※低く仕立てすぎると、翌年の開花に影響する場合があるため、1年に少しずつ調整していくのがおすすめです。
②樹形を整えたい場合の仕立て方
金木犀の樹形には3つの形があります。
・玉仕立て
・長玉造り
・盆型
それぞれの特徴は以下の通りです。
お庭の雰囲気や目的にあわせて、樹形を選びましょう。
玉仕立て(たまじたて)
・球状に丸く整えるスタイル
・柔らかく親しみのある印象に
・和風・洋風どちらの庭にも合いやすい
長玉造り(ながだまづくり)
・玉仕立てよりも縦に長い球状
・スラっとした印象で、狭いスペースにも◎
盆型(ぼんがた)
・上部が平らで広がりのある形状
・通気性・採光性が高く、害虫予防にも有利
剪定の失敗例とその回避法

丸坊主にするのはNG
勢い余って全体をバッサリ切ってしまうと、回復に時間がかかり翌年の開花がゼロになることも。
金木犀は繊細な樹木のため「剪定は適度に行う」が鉄則です。
枝枯れに注意
切り口が雑だったり、太枝を切った後に保護しなかったりすると、切り口から菌が入り枝の枯死につながるケースもあります。
滑らかな切り口と癒合剤の使用を心がけましょう。
切りすぎに注意
全体の3分の1以上を切ると木にダメージが残ってしまいます。
そのため、1回で完璧を目指さず、数年かけて整えるつもりで剪定して木の負担を軽減するのが安全です。
プロが教えるワンランク上の剪定アドバイス
一般的に金木犀の剪定に対するアドバイスとしては以下の3点があげられます。
・剪定は木との対話。枝の生え方を読み取ることが重要
・無理に整えすぎないのが美しい金木犀のコツ
・剪定後1週間ほどは肥料を控えめにして、木の回復を見守る
これを踏まえたうえで、お庭番守ではお客様ファーストでご希望に沿った形の剪定を行っております。
たとえば時期や樹勢などで剪定のやり方を変えていることもあります。
木は一本いっぽん異なっているため、明確な正解というものが存在しないからです。
またそこにお住まいのお客様のご要望も大切であるため、すべてが同じやり方で剪定すれば良いわけではないと考えております。
こだわりのある職人さんのなかには「この枝は残さなきゃダメだ」というのもあり、木にとってはそれもとても大切なことであると理解しているのですが、「お客様が切って欲しい」というご希望がございましたら、今後のリスクの可能性を通知したうえで、切らせていただくこともあります。
このように適切な時期・方法・道具を選び、焦らず丁寧に整えていくことと、お客様のご要望を合わせた形で整えることが、美しく気持ちのいい庭木を保つ秘訣です。
プロが教える剪定テクニック
誰でもできる剪定のコツ
・太枝は根元から
・細枝は芽の上5mmでカット
・内向きの枝より外向きの枝を優先
金木犀に特化したテクニック
・花芽ができる「短枝」は極力残す
・翌年の花を増やすには、前年の剪定が命
プロは「来年の姿」を想像しながら、全体のシルエットを描くように剪定しています。
刈り込みの場合、仕上げで見えるところはよく切れる大鋏で切っている点(トリマーだけだと切り口が美しく見えないこともあるので仕上げは大鋏のを使用してより綺麗な切り口になるように心がけています)。
また、すいたりする場合でしたら、幹に沿って斜めに切ることで、より美しい切り口に見えます。
金木犀と害虫の関係|剪定で病害虫予防もできる?

金木犀につきやすい代表的な害虫とその特徴
金木犀には以下のような害虫がよく発生します。発見が遅れると葉や枝が枯れ、花付きが悪くなる原因にもなります。
カイガラムシ
枝や葉に白〜茶色の小さな殻のような虫が付着。樹液を吸って弱らせ、排泄物によって「すす病」も併発しやすい。
ハダニ
葉の裏に小さな赤い点のように現れ、葉がかすれたような見た目になる。乾燥時期に発生しやすい。
アブラムシ
若い枝や葉の先端に集まり、群がって吸汁する。これもウイルス病やすす病の原因に。
剪定が害虫対策に効果的な理由
剪定には、金木犀の見た目や花付き改善だけでなく、害虫の発生を防ぐ効果もあります。
理由は以下のとおりです。
・枝が混み合うと風通しが悪くなり、害虫や病気の温床に
・害虫が潜みやすい古枝・枯れ枝を除去することで発生源を断つ
・光が入りにくい場所ができると、湿気がこもり病害虫にとって快適な環境になる
害虫が発生した場合の対処法
剪定だけでは防ぎきれない場合、以下のような対処法も有効です。
・薬剤散布(例:オルトラン、スミチオンなど)を剪定後に実施する
・高圧シャワーで葉裏を洗い流す(ハダニ・アブラムシ対策)
・冬季に「マシン油乳剤」を使うとカイガラムシ対策になる
予防のために定期的な点検と剪定を
年に1〜2回の軽い剪定と、春〜秋の定期的な害虫チェックを習慣化することで、金木犀の健康を長く保つことができます。
剪定の実例紹介
※弊社で実際に剪定を行った庭木施工事例はこちらからご覧いただけます。
・倉敷市浜ノ茶屋にてツツジ・金木犀の剪定を行いました【施工事例】
・庭木の伐採 倉敷市児島赤崎倉敷市児島赤崎にて庭木(サクランボ・金木犀・クロガネモチ)の伐採を行いました【施工事例】
・倉敷市藤戸町天城にて庭木の伐採を行いました【施工事例】
まとめ
金木犀は放置しておくと見た目が乱れ、花も減ってしまいます。
自分で剪定することもできますが、正しい知識と道具、そして経験が必要です。
失敗すると花が咲かなくなることもあるため、不安な場合は専門の剪定業者に依頼するのが安心です。
当メディアを運営するお庭番守では、金木犀の剪定も行っておりますので過去の施工事例などをご覧のうえご依頼いただけましたら幸いです。
大切なお庭の金木犀。
適切な時期と方法で剪定し、来年もきれいな花を咲かせましょう。