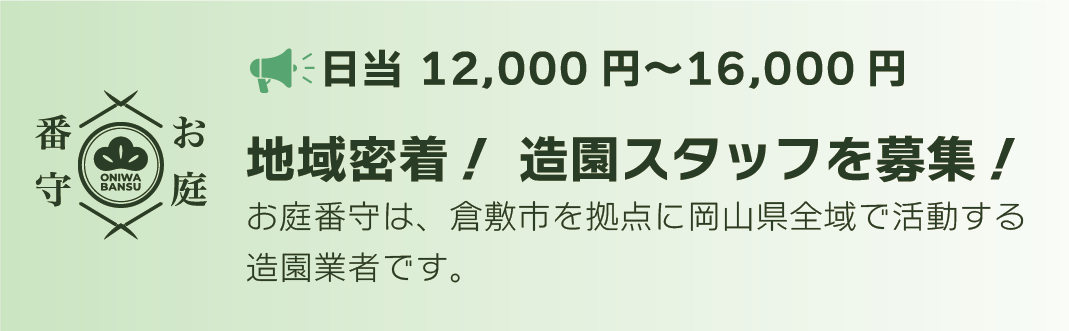剪定時期は「冬季」と「夏季」
樹木の剪定は種類によって適している時期が異なります。

剪定をする時期は大きく分けて2つ。
春に備えた「冬季」の剪定と、伸びすぎた枝や葉を剪定する「夏季」の剪定です。
ただし、ここでいう「夏季」とは夏の盛りのことではなく、夏を迎える直前という意味ですのでご注意ください。
選定を避けるべき時期
「真夏」は樹木が一年で一番活発に成長しているタイミングであり、樹木にとってもっとも体力が消費される時期であるため、剪定を避けたほうが良いでしょう。

そのタイミングで剪定を行ってしまうと、枝などから樹液が漏れ出てしまい木に大きなダメージを与えてしまいます。
また、この時期に枝葉を切り落としてしまうと、庭木が切り落とされた分だけ成長をしようとして、養分を消費してしまうため弱ってしまいます。
真夏以外にも、「4〜5月」「7〜8月」は剪定を避けるようにしてください。
常緑樹は冬に切るな
樹木は大きく3つの種類に分けられます。
・常緑針葉樹
・常緑広葉樹
・落葉広葉樹
そのなかでも、落葉せずに一年を通して緑の葉をつける常緑樹は冬に剪定してはいけません。

体内に養分を蓄えることが得意ではないため、つねに必要な分だけ光合成をして養分を作っているため、日照時間が少なく光合成が少なくなってしまう冬に剪定をしてしまうと、途端に弱ってしまいまうのです
「常緑樹は冬に切ると風邪をひく」
こういった言葉もあるほどですので、ご注意ください。
「大つち・小つち」の日
古来より、「大つち・小つち」のタイミングで木を切ると、虫が入ったり腐りやすくなると言われています。
そのため、その時期(「大つち・小つち」ともに7日間)に剪定をすることはNGとされています。

具体的な日にちは、その年によって異なります。
大つち
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間。
小つち
戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日
ご自身で庭木の剪定をされる方は、その年の「大つち・小つち」がいつなのか選定の際は必ずチェックするようにしましょう。
土用も剪定禁止
土用の丑の日などで有名な「土用」も庭木の剪定には適さない時期です。
土用は年に4回あります。
それぞれ、立春・立夏・立秋・立冬のまえの18日間を指します。
この時期は、土が活発になるため、枝の伐採などしてはいけないと言われています。
樹木別剪定時期

樹木は大きく3種類(常緑針葉樹、常緑広葉樹、洛陽紅葉樹)に分かれます。
それぞれに適した時期に剪定しましょう。
常緑針葉樹
常緑針葉樹の剪定適期は「3月~4月ころ」です。
以下の樹木が常緑針葉樹にあたります。
スギ
マツ
コニファー
ヒノキ
カイヅカイブキ
コノテガシワ
ただし、常緑針葉樹は不要な枝を切る程度の軽い剪定であるならば、本格的に冬を迎えるまえの時期「10月~11月ころ」に剪定をしてもかまいません。
常緑広葉樹
常緑広葉樹の剪定適期は「3月~4月」と「5月下旬~6月ころ」です。
以下の樹木が常緑広葉樹にあたります。
キンモクセイ
サザンカ
ツバキ
カシ
サツキ
アオキ
アセビ
シマトネリコ
ソヨゴ
オリーブ
クリスマスホーリー
ナンテン
レッドロビン
これら常緑広葉樹は寒さに弱い樹木です。
冬場の剪定には向きませんので「夏季」に剪定を行いましょう。
落葉樹広葉樹
落葉広葉樹の剪定適期は「12月~2月ころ」です。
以下の樹木が洛陽紅葉樹にあたります。
ヤマボウシ
ハナミズキ
モミジ
アオダモ
アホハダ
アジサイ
エゴノキ
カキ
ジューンベリー
ユキヤナギ
洛陽紅葉樹は樹木が活発に成長する時期である「4月〜5月」「7月〜8月」の剪定は避けてください。
枝を切る程度の軽い剪定ならば、樹木の成長が落ち着いた「3月」「6月」「9月〜10月」に行うことが可能です。
庭木の剪定に便利なアイテムとは

庭木の剪定の負担を減らすためには、専用の便利アイテムを使用するのが有効です。
ここでは、庭木の剪定に便利なアイテムを6つ解説します。
庭木の大きさや種類によって適しているアイテムが異なるので、アイテムを選ぶ際には、使用するシチュエーションや樹木の種類を明確にするように心がけましょう。
剪定ばさみ
剪定ばさみは、庭木の枝を剪定するために開発されたハサミです。
握りやすいグリップと鋭い刃が特徴で、力を入れずに作業が可能なため、樹形を整えたり、風通しを良くするのに最適です。
軽量タイプやロック機能付きなど種類も豊富で、初心者でも扱いやすいため、ガーデニングのあらゆる場面で活躍できます。
剪定ノコギリ
剪定ノコギリは、剪定ばさみでは切れない太めの枝をスムーズに切断できる道具です。
鋸刃には細かなギザギザがあり、軽い力でもしっかりと枝に食い込んで切り進められます。
折りたたみ式やカーブ刃タイプなど種類が豊富なため、使い勝手の良さを重視したい人でも問題なく使用できます。
高所の枝や密集した箇所の剪定をしたい人は、ぜひ持っておきたいアイテムだといえるでしょう。
刈り込みばさみ
刈り込みばさみは、生け垣や庭木の枝葉を一度に広範囲カットできる道具です。
長い刃と両手で操作する構造により、均一な仕上がりが実現しやすく、見た目を美しく整えやすいです。
細かな調整よりも全体の形を整える作業に適しており、生け垣や庭木を効率よく剪定を進めたい人にぴったりなアイテムだといえるでしょう。
植木ばさみ
植木ばさみは、細かな剪定作業に適した園芸用のはさみです。
刃先が細く、狙った部分を的確に切れるため、若い枝や芽のカットなど、樹形を丁寧に整えたいときに最適です。
盆栽や小型の庭木の手入れにもよく使われ、繊細な作業に向いています。
高枝切りばさみ
高枝切りばさみは、地面に立ったまま高い位置の枝を剪定できる道具です。
長い柄が特徴で、手の届かない場所も安全にカットできるため、脚立を使わずに済み、転倒などのリスクを減らせます。
軽量で扱いやすいタイプや、刃にノコギリが付いた多機能モデルもあり、高所の枝の整理に最適です。
枝を切ることで日当たりや風通しが改善されるため、庭木の健康維持にもつながる、頼れる剪定アイテムだといえるでしょう。
掃除道具
剪定後のゴミを掃除する際には、以下のアイテムを使用するとよいでしょう。
- 熊手
- 竹ぼうき
- 箕(大きなちりとり)
ゴミを放置したままにすると、虫が湧いてしまうので、効率よく掃除することが大切です。
選定の種類

透かし剪定
数ある剪定方法のなかのもっとも基本的な剪定方法。
植物の不要な枝葉を落として間引きする方法で樹木の形を整える目的の他、日当たりや風通しを良くする効果も期待できます。
整姿剪定
こちらも基本的な剪定方法。
植物の外観や樹形を整えるために余分な枝葉を切り落とす方法です。
植美しい形状を保つために植物の成長に合わせてカットしましょう。
切り戻し剪定
庭木の高さを抑えるには切り戻し剪定を行いましょう。
切り戻し剪定とは、樹冠を一回り小さくする剪定方法。
全体的に枝を大きく(1/2~1/3程度)切ることで木が高くなりすぎないようにします。
樹形を保ったまま樹冠を小さくする方法や、形自体を作り直したりする方法がありますので、好みに合った方法をとりましょう。
切り戻し剪定をすると樹木が栄養をたくさん作るようになるため、より強い枝葉の成長が期待できます。
芯止め剪定
植物の主枝の先端にある成長点と呼ばれる場所を切ることで、枝がうえに向かって伸びていくのを防ぐ剪定方法。
芯(樹木の中心部分)を止めることで、植物が横方向に広がりやすくなり樹木全体の形が整います。
切り取った部分のしたにある芽が成長を始め、枝が増えるため、樹木の密度が増してボリュームのある形に整いますよ。
切り詰め剪定
枝の先端をカットして短く整える剪定方法。
この方法では余分な枝を適切な位置で切り詰めることで、木の重要な部分の成長を促します。
樹形を整えるために行われる方法です。
刈り込み剪定
刈り込みバサミを使用して庭木や茂みを短く切り揃える剪定方法。
背の低い植栽や規模が小さい植栽に用いることが多い方法です。
花がら摘み
花がら摘みは、花の枯れた部分を摘み取る剪定方法。
刃物を使う場合と使わない場合がありますが、目的はどちらも同じです。
植物のエネルギーを新しい花の成長に向けることができるので、長期間花を楽しむことができます。
剪定時期を間違えたときのリスク
剪定時期を間違えると、せっかく育てた庭木がさまざまなトラブルに見舞われてしまいますのでご注意ください。

起こり得る、おもなトラブルは以下の4つ。
・花が咲かない
・枝が枯れる
・忌み枝(本来伸びる方向とは違う方向に伸びた枝)が残る
・樹形が乱れる
そもそも幹や枝を切る行為である剪定は樹木にとって大きなダメージになります。
そのため、極力、負担を軽減させることが大切です。
また、剪定のダメージを回復するためには時間がかかります。
最悪の場合、木が枯れてしまうこともありますので気をつけましょう。
剪定時期を間違えてしまったときの対処法
もし不適切な時期に剪定をしてしまった場合、すぐに木全体が枯れるわけではありません。
しかし、時間がたつにつれて木は徐々に枯れ始め、そのまま放置すると枯れた枝が腐って病気や害虫の原因になることがあります。
万が一、剪定時期を誤って枝の一部が枯れてしまったときは、すぐにその部分を切り落として対応してください。
そして、そのあとはできるだけ木に負担をかけないようにし、自然に枝葉が再生するのを待ちましょう。
それでも心配でしたら、早めに専門業者に相談してくださいね。
まとめ
庭木の剪定には、適切な時期があったりするだけでなく、綺麗に整えるためにはそれなりの技術とセンスが必要になってきます。
簡単な剪定ならば自身でできるケースもありますが、時間も体力も使ううえ、周囲の住宅に迷惑がかからないように配慮しなければいけません。
そのため、業者に頼むのが確実な方法になってきます。
どれくらいの料金がかかるのかなど、直接相談してみてはいかがでしょうか。